
みなさんこんにちは、Camp1プロダクトチームのBruceです。現在、私はフリマアプリ「メルカリ」のプロダクトマネージャー(PM)として、お客さまの購入体験を向上させるためのUX機能開発を担当しています。
メルカリでは中途・新卒問わず海外採用を行ってきました。それもあり、メルカリは国内外で成長し続けています。
私は、外国籍の新卒メンバーとして、今回この記事を書いています。私にとって1社目の会社となるメルカリでの体験を通じて、海外の環境で働くことへの不安や心細さを抱えている方々へ希望やインスピレーションを与えることができればと思っています。
これからこの記事に書くのは、メルカリで誕生した私のキャリアストーリーについてです。
※撮影時のみマスクを外しています。
この記事に登場する人
-

Bruce Liangメルカリでプロダクトマネージャーを務める。台湾系アメリカ人一世としてアメリカで生まれ育ち、出まれた時から多国籍文化の環境で育つ。2017年、イーベイ・ジャパンのインターンシップで初来日を果たす。その後、2018年にカリフォルニア大学サンディエゴ校で心理学の学士号を取得。技術的な経験はなく、日本語能力も限定的ながら、お客さまへの重視と価値ある製品の創造に強い関心を持ち、2018年10月にメルカリJPに新卒のプロダクトマネージャーとして入社。
「クビになる」かもしれない…?言語とスキルの壁に悩んだ日々
入社1日目に心に浮かんだこの言葉を、今でも忘れることはありません。
当時の私は数週間前に日本に来たばかりで、自分の置かれている状況をあまり理解できていませんでした。最初は、アメリカから日本のような馴染みのない国に引っ越して新生活を送ることや新たな環境で仕事をすることは、簡単で楽しいものだと考えていたのです。おそらく当時の私は学生意識が抜けず、無意識のうちに「なんとかなるだろう」「心配することはないだろう」と期待していたのだと思います。初めてフルタイムの仕事で大人の世界に入っていくことは、新しい学校に通うことと同じだと思っていました。
初めてチームにジョインする日まで、私はそんな考えを持ち続けていました。当時のメンターである金さんは、チームにおけるPMへの基本的な期待値などについて、とても辛抱強く優しく教えてくれました。また、私が安心してすべてを理解できるように、英語を使って話してくれました。
最初の配属先だったBuyer UXチームでは、お客さまの購入を増やして最終的にはGMVを向上させるべく、本番アプリでリリースする機能やプロジェクトの作成を中心に担当。PMとしてプロジェクトアイデアの提案書を作成し、開発可能な仕様に変換することでエンジニアに実装してもらったり、最後にプロジェクトリリースの結果を分析したりしていました。ちなみに、チームのマネージャーだった富島さんがメルカリの共同設立者であることはあとになってから知りました。求め得るすべての機会を与えてもらいましたし、キャリアをスタートさせる環境としては充分でした。
しかしこのときにぶつかったのは、言語の壁。書類や入社時の資料、業務で必要なドキュメントはすべて日本語で書かれており、私には全く理解できませんでした。私は冷静な態度を装っていましたが、心の中はパニック。その前の週に行われたベーシックトレーニングでは、通訳を必要とする唯一の新卒としてすでに困難に直面していました。
他の同僚とは異なり、自分はサポートなしにはベーシックトレーニングさえ終了できないことに気付き、私は日本において、チームメンバーから信頼されるPMになる術はないだろうと思いました。社会人としての責任を背負うとはどういうことなのか、そしてそれが自分の想像といかに異なるのかに気付かされました。この新しい環境でチームや同僚を失望させることだけでなく、国を離れる前に私を応援してくれた友人や家族をも失望させてしまうのではないかと恐怖があり…、誰も失望させたくなかったのです。そんな思いを抱え、あるときは個室でベーシックトレーニングの講師の前で取り乱してしまったことがありました。これらはある意味、いよいよ大人の世界に入るためのウェイクアップコールのようなものでした。
私は質問をしたりメンターやマネージャから指導を受けたりしながら、日々の業務に取り組んでいました。最も賢いやり方だったとは言えませんが、経験や語学力の不足を補うために深夜までオフィスに残り、SQLや基本的なプロダクトマネジメントの勉強をする日々を過ごしました。疲れ果ててデスクで寝落ちしてしまうことも度々ありました。
異動の打診、守りたかった約束
しかし残念ながら、その日が来ることはありませんでした。 新しい職場環境とPMとしての責任の重さにもがきながら2四半期が過ぎた頃、上司から声をかけられました。所属していたチームでの業務、は私には荷が重すぎるのではと、チーム異動変更の打診を受けたのです。その頃、私は初めてプロジェクトをリリースし、その直後にお客さまからサービスの問題を指摘される大失敗を経験していたところでした。
それでも、私はチーム異動変更の打診を断りました。
当時はメンターの金さん、菱井さん、行徳さんで構成されていたチームの中で、他のPMに自分がついていけていないことは明らかでした。それでも、チームを異動する変えるということは、逃げ出すようなものだと強く感じたのを覚えています。
マネージャーの富島さんは私の意思を尊重してくれ、代わりに新しいチャレンジを提案してくれました。それが、四半期かけてQAテストの基礎を集中的に学ぶことでした。
QAテストとは、基本的には「品質保証テスト」のこと。モバイルアプリケーションが全体として正しく動作しているか、あるいは機能自体が仕様書に記載どおりに動作しているかを確認します。アプリ開発の基礎的な知識を適切に身に着ける良い機会になると思い、最初はワクワクし、彼の提案に同意しました。
しかし数ヶ月後が経つにつれて、残念ながらQAテストが自分に向いていないことがわかりました。当初の目標であった機能リリースのプロセスや製品の機能の仕組みといった基礎知識を学ぶことはできましたが、それ以上にQAについて学び続けるモチベーションを維持することはできませんでした。私の性格は、クリエイティビティやコラボレーション寄りであると気付いたのですが、それは、オフィスで一人で何日も黙々と機能をテストすることではなかったのです。そして、それでは表現できないと感じました。四半期の終わり頃になると、私のモチベーションはさらに下がりました。お客さま向けの製品を作るクリエイティブな方に戻りたい、たとえその実現に向けて何をすべきか知らなくてもそうしたいと強く感じたのです。
四半期が終わり、年2回のパフォーマンス評価の時期が来ました。その時のマネージャーの目を、私は今でも鮮明に覚えています。
評価レポートの共有は、まずは私のパフォーマンスに関するポジティブな内容から始まりました。しかし改善点のセクションに入ると、彼の目が変わりました。具体的に、彼は四半期を通じて私を指導し見守ってくれたQAメンバーのピアレビューを読み上げたのですが、2人からはとも私のパフォーマンスやモチベーションが下がっていると指摘されました。そして、落胆していたことが明確に記されていました。それは重要な話だったのにも関わらず、私の耳にほとんど入らず、むしろ彼の目から視線を逸らすことができませんでた。そこには、完全なる失望が映っていたのです。
彼は最後に、その時まで心から私を信じていたと言いました。今度はその言葉がはっきりと聞こえました。彼は私を信頼し、自身の過去の苦い経験を詳しく話してくれたほか、絶えず私個人とその成長を期待してくれていたことを覚えています。最も心を痛めたのは、私が自分の期待や約束を果たせなかったことではなく、口には出さなくてもチームに入った瞬間から私を心から信じてくれていたチームみんな人の期待を裏切ってしまったことでした。
セッション終了後、私は顔をあげられずに黙ったまま評価を受け入れ、その日は荷物をまとめて会社を出ました。その後もしばらくショックは残っていましたが心の傷は癒えませんでした。一方でもう一度やり直したいという強い気持ちがあったのも覚えています。私を信じてくれた彼が間違っていなかったことを証明したかったのです。
尊敬していた人との別れ、そこから生まれた約束
その評価の直後、富島さんは徐々にチームとの関わりを減らし、アプリの新しいHome体験を作るための作業に集中するようになりました。これは後に、初の大規模なHome Revampプロジェクトとして知られるようになるものです。そのわずか数ヶ月後、彼の退職が発表されました。私は悲しみに打ちひしがれました。
私は自分のつまずきから立ち直り、彼の私に対する信頼が間違っていなかったことを証明しようと密かに努力していたことを伝えられませんでした。私を信じてくれたことが心に強く残り、彼が会社を辞めたその日、私は自分自身と約束をしました。メルカリに残って彼のようなマネージャーになり、いつか自分もプロダクトチームを率いて、彼が追い求めていたUXの大幅な改善で業績を爆発的に伸ばしていきたい。彼が始めたことを最後までやり遂げたい。そんな思いが今も私の原動力になっています。
彼の送別会で最後の挨拶をしたとき、私には涙ながらに謝ることしかできませんでした。
 社内のSlackアイコンは富島さんの送別会で集まったときに撮ったものを使っています
社内のSlackアイコンは富島さんの送別会で集まったときに撮ったものを使っています
飛び立ち
富島さんの退職後は、與田さんが私の新しいマネージャーになりました。現在も引き続き彼にレポートしています。富島さんと同様に、與田さんはPMとしての可能性だけでなく、会社に貢献する貴重なメンバーとして私を信頼してくれました。
当時、メルカリでは開発プロセスのアジャイル、特にスクラムを導入し始めていました。その一環として、スクラムの指導に特化したアジャイルコーチを試験的にプロダクトチームに配属し、マネージャーの與田さんは私をスクラムマスターに割り当てることにしました。
それまでは、認定トレーニングを受けた正式なスクラムマスターが社内におらず、私はその新たな責任のすべてをこなせるかどうか確信が持てませんでした。また、PMとしての職務にもまだ十分に慣れていませんでした。

スクラムマスターは、基本的にはIT企業のファシリテーター的な役割であり、実際のお客さまへのリリースを行うチームを中心とした製品チームのチームワークと開発プロセスの改善が期待されています。そのため、常にフラットな視点を維持しながら、チームをまとめてコラボレーションを維持するという大きな責任を担います。場合によっては、PM以上の責任を負うこともあります。
プロダクト開発のマネージャーになる約束を果たせていなかったため、最初はこのポジションを引き受けることに若干の抵抗がありました。しかし、私のように経験の少ない者にとって滅多にない成長の機会だし、過去の失敗を補うためには私にはしなければならないことが多くあるとわかっていました。そう思っていた私は、このチャンスに挑戦することにしました。難しいことは覚悟の上で、PMとスクラムマスターの兼務ができないかどうか、マネージャーに相談しました。最終的には、一応の承諾を得られました。
その後すぐに、田中さんとアンドレさんの2人のアジャイルコーチから個人指導とメンタリングを受けることになり、数ヶ月間の指導と試行錯誤を経て、社内初となるスクラムマスターになる方法を学ぶことができました。開発チームを取り纏めるファシリテーターとなり、意義ある製品をリリースするという統一された目標に向かって体系化されたプロセスの中で業務を行うようになったことで、私自身の製品への理解を深めることができ、PMとしての能力を高めることにつながりました。その後、2つの役割を改善していく取り組みを少しずつ行った結果、私のスキルや能力に大きな影響がもたらされました。今では、プロダクトマネジメントを一人で遂行できるようになっています。
飛べなかった雛鳥が、ようやく自力で飛び立てる小鳥に成長できたのだと思います。振り返ると、私はこの経験から3つの貴重な教訓を得ました。
・ 何度転んでも決して引き下がらないこと。
・ 不安や恐怖を感じても、チャンスが来たら受け入れること。
・ 自分を信じてくれている人を信じること。それは、心の中に停滞感があるときに、自身を鼓舞してくれることになります。
ゼロからイチへ、イチから無限へ
富島さんの退職前に彼から譲り受けた本を今でも持っています。その本のタイトルは『ゼロ・トゥ・ワン:君はゼロから何を生み出せるか』です。 アメリカでは非常に有名なこの本は、最も有名なベンチャーキャピタリストの一人であるピーター・ティールが書いたものです。その名の通り、この本はスタートアップの成功の秘訣を記した初心者向けのガイドのようなものですが、私がこの本を手元に残す意味は本書の本来の目的とは異なるところにあり、それは本のタイトルによく表されています。
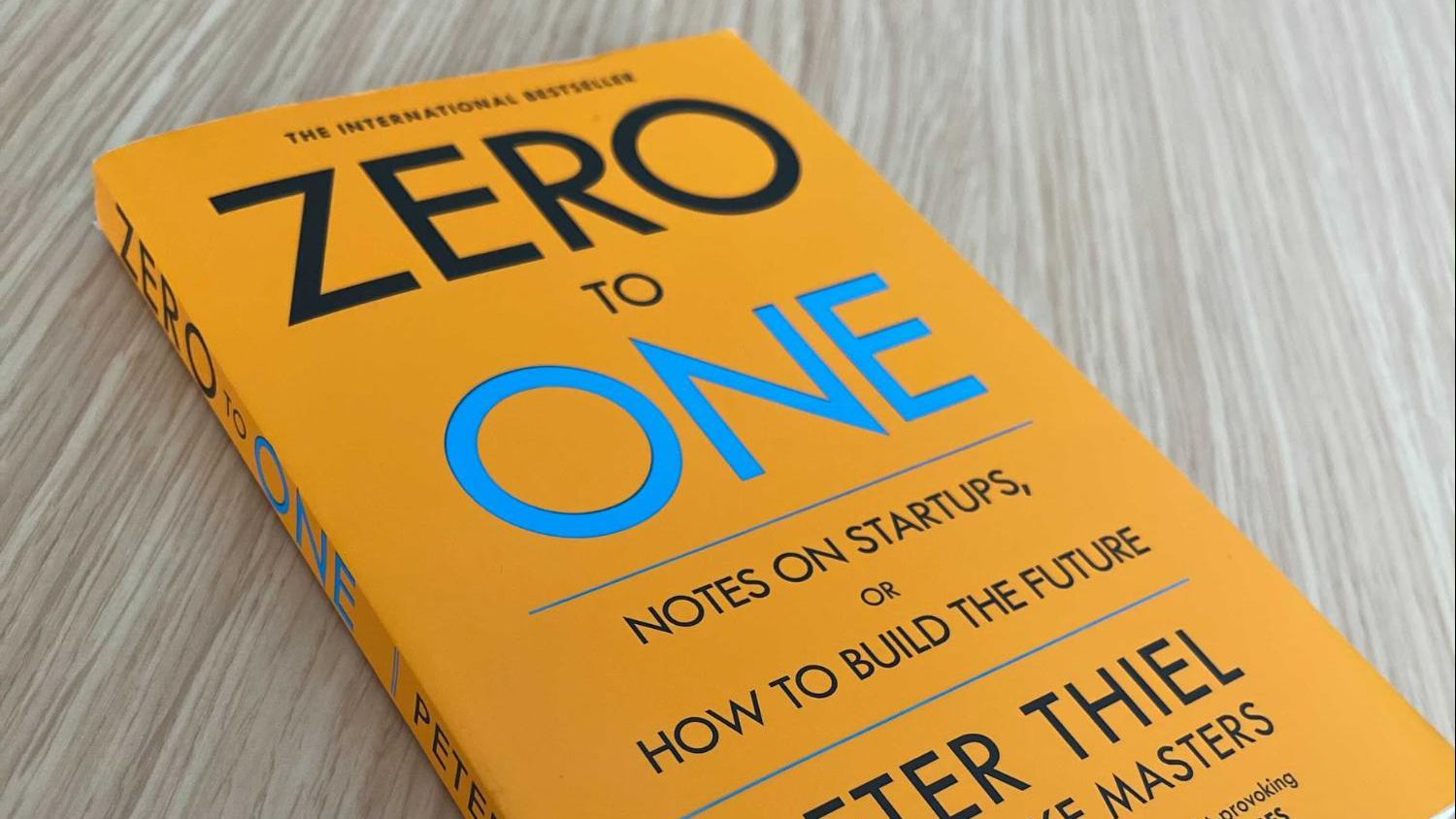
この本では、スタートアップが「ゼロからイチ」の壁を超える時に最も重要なことが記されており、実際に多くのスタートアップが失敗する理由は、成功に向けて常に最も重要なステップとなる最初の一歩にあります。その一例として、本の中では最初のiPhoneのリリースについて語られています。のちにAppleはiPhoneの後継機種でも大きな成功を納めていますが、このすべての源泉となるのは、最初のステップとしてSteve Jobsによる伝説のプレゼンテーションです。
本書で記されている考え方と同様に、私はキャリアにおいて最も重要なことは、ゼロからイチへの壁を超えることだと思います。私自身の経験を例に挙げると、一番大変だったのは、最初の苦労や不安を乗り越えて、わずかな足掛かりを得ることでした。最初の試行錯誤や失敗を経て、ようやく物事のコツをつかめたとき、私の成長と学びはそこから今日に至るまで飛躍的に成長していきました。その成長は必ずしもきれいな直線的なものではありませんでしたが、ゼロからイチへのジャンプを経験したことで、今ではこれからの成長は無限だと感じられるようになりました。
私の経験だけではなく、メルカリのその他のメンバーを見ていても、この現象は当てはまることだと思います。最初の一歩ほど怖くて難しいことはありませんし、そこでもがいている人の気持ちが私にはわかります。しかし、目標や夢を達成するためには避けて通れない道であり、誰もがいつかは成し遂げたいと願う大切な目標を持っていると思います。あとは、一歩前に踏み出す勇気を持つだけです。
その先に何を達成できるのかは、誰にも占うことはできません。可能性は無限に広がっています。


