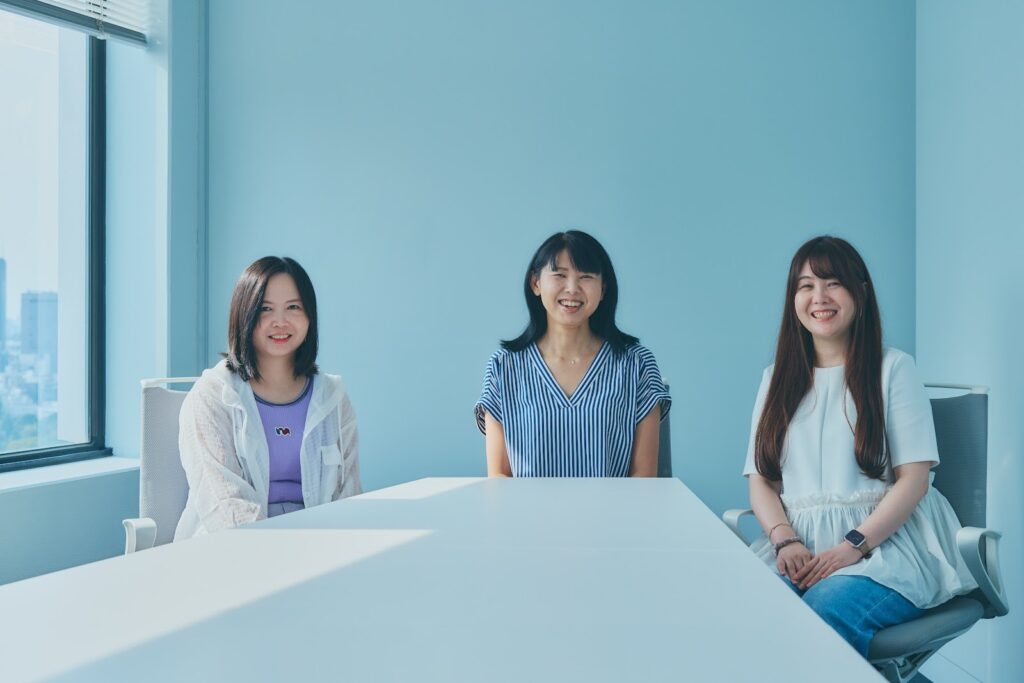生成AIの登場により、あらゆる業界で業務変革の波が訪れています。それは、専門知識が求められる企業法務の世界も例外ではありません。メルカリのLegalチームは、この1年でAI活用を急速に推進し、今や業務に不可欠なツールとして定着させています。
「AIをどう使えばいいか分からない」ほど手探りの状態からスタートしたそうですが、どのように普段の業務へ導入していったのでしょうか。
本記事では、メルカリLegalチームの落合由佳(@Yuka)、瀬谷絢子(@seya)、Teitei Ryu(@avaliu)に、AIに対する心理的な壁を乗り越え、チーム全体を巻き込みながら活用を推進してきた軌跡について、具体的な取り組みや工夫を交えて話を聞きました。
プロフィール
この記事に登場する人
-

落合由佳
日本電気株式会社を経て、ソフトバンクグループ株式会社に入社。法務として、ボーダフォン日本法人やダイエーホークス等の企業買収案件や、多数の海外投資案件、資金調達案件を担当。その後、スタートアップに飛び込み、会社の立ち上げを経験。オープンドア株式会社の法務部長を経て、メルカリに2020年1月入社。Legalを経験後、現在は、AI Governance teamとIP&New Laws teamのマネージャー。全社のAI Task Force PMOも兼務。ニューヨーク州弁護士。ペンギンおたく。夢は南極旅行。
-

瀬谷絢子
柳田国際法律事務所、株式会社オプト法務部を経て、2018年7月にメルカリへ入社。Legal Operations team Manager。
-

Teitei Ryu
中国弁護士資格取得後、2013年に日本へ移住し、IT企業等で法務を経験。2024年12月にメルカリへ入社し、現在はリーガルで定常業務の他、AIを利用してナレッジ蓄積やオペレーション改善の取り組み等を担当。
すべては「どう使えば…?」の手探りから始まった
―まず、LegalチームでAIの活用を始める以前は、どのような状況だったのでしょうか?
@seya: 私たちのAI活用は、2024年5月にコーポレートエンジニアリングチームの主催で開催された、AI/LLMが適用可能な領域を特定するワークショップに参加したところから始まりました。そこで初めて「どうやらAIが業務に使えるらしい」と知ったのが正直なところです。
そのワークショップの後、学んだことをチームに展開するように言われたのですが、当時の私一人ではどう持ち帰れば良いか分からず…少し途方に暮れていました。2024年7月時点では、チームの過半数がAIに関心はあっても利用したことがない、という状況でした。

―まさにゼロからのスタートだったのですね。
@Yuka: はい。ワークショップ自体は非常に有益でしたが「自分たちが日々どう使うか」という具体的なイメージを各自が持つことが、次のステップとして非常に重要でした。そこで私は2024年の8月に、まずLegalチームメンバーのAIへの心理的なハードルを下げることを目的とした『AI初心者セミナー』を開催しました。
心理的な壁を壊した「Wow!と思う体験」
―どのようなセミナーだったのでしょうか?
@Yuka: コンセプトは“AIと友達になる”です。「要約」や「英訳」「(文章の)清書」といった、誰でもすぐに使えるような、短くて、簡単なプロンプトを紹介し「たった2文字のプロンプトでも業務がこんなに楽になる」という威力を実感してもらうことを目指しました。
新しい技術に対しては、誰もが「どうしたらいいか」と戸惑ってしまいます。だからこそ、ハードルをできる限り低くして、まずは一歩を踏み出してもらうことが何よりも大切だと考えました。
―参加されたメンバーの反応はいかがでしたか?
@Yuka: 参加しているメンバーの表情がぱっと明るくなり、「こんなこともできるのか!」と感嘆の声が上がりました。アンケートでも「感動した」という感想が多く寄せられ、この“Wow!と思う体験”が、みんなのマインドセットを変える大きなきっかけになったと確信しています。このセミナーを機に、毎日AIを使うようになったメンバーも多く、チーム全体の心理的な壁が大きく下がったのを感じました。

アイデアを形に。熱量を高めた「AI/自動化ハッカソン」
―チームの雰囲気が変わった後、次のステップとして取り組まれたことは何ですか?
@Yuka: 個々人がAIを使いこなせるようになってきた段階で、次なる挑戦として『Legal & Governance Division AI/自動化ハッカソン』を企画しました。目的は、個人利用のレベルから一歩進んで、「AIや自動化で、さらに業務の効率化や新しい価値創造を実現し、生産性を上げる」という領域にチームで挑戦することです。
―ハッカソンという形式には、何か狙いがあったのでしょうか?
@Yuka: 重要なポイントは、2週間の開発期間後、発表会を設け、各チームが自分のアイデアのプロトタイプのデモを実際に披露し、VP(執行役員)も参加して評価される場を設けたことでした。普段一緒に仕事をしているメンバーの前で発表する以上「良いものを作りたい」「恥をかきたくない」という気持ちが生まれ、皆さんのモチベーションが自然と高まったのかなと。「発表するからには、ちゃんと機能するものを作らなければ」という意識が働き、チーム同士が切磋琢磨する良い機会となりました。
この取り組みを通して、17件の実践的なアイデアのプロトタイプが生まれました。
ハッカソンで生まれたプロトタイプのデモ *動画内のチェックリストと利用規約はダミーです
日常業務への実装、どう進めた?
――ハッカソンで生まれたアイデアは、その後どうなったのでしょうか?
@Yuka: 次のフェーズとして『Project Everyday AI』を始動しました。これは、ハッカソンで作ったAI活用事例のプロトタイプなどを、毎日の業務に本格的に「実装」することを目的としたプロジェクトです。日々の業務にAIを根付かせることで、「毎日AIを使う」状態を目指しました。
@avaliu: 私もこのプロジェクトに参加しました。例えば「法律事務所との相談のやり取りメールを相談トピックごとに整理したい」といった、現場の具体的なニーズを形にしていきました。その過程で @Yuka さんから「まずはミニマムで稼働するもの(MVP:Minimum Viable Product)を作ればいい」というアドバイスをもらい、試行錯誤を重ねて仕組みを完成させました。最小限の形でまず動くものを作ることの重要性を学びましたね。

未来を描く「AI-Native Roadmap」の策定
ーそこから「AI-Native Roadmap」を策定されたのですね。このロードマップの概要と、策定の背景、目的について教えてください。
@Yuka: AIの登場によって、人間の仕事は大きく変わると考えています。ルーティンワークをAIに任せ、人間は戦略策定、意思決定やネットワーキングといった、より付加価値の高い業務にシフトしていくことになるでしょう。この考え方を私たちの業務に当てはめ、「3年後、AI導入によって業務がどうなっているか」を示した、『AI-Native Future Vision』を作成しました。

『AI-Native Future Vision』では、自分たちのメイン業務をタスクレベルに細かく分解し、「これはAIに任せる」「これは人間がやる」「人間は創出された時間でこの業務を行う」というように割り振りました。例えば、生成AI利用ガイドライン作成業務であれば、情報収集やガイドライン案の作成はAIに任せ、人間はガイドライン案のレビューや社内調整を行い、また、余裕ができた時間で戦略立案を行うといった形です。実はこれも、「〇〇業務をタスクに分解し、各タスクについて、『AIが担う業務』と『人間が担う業務』を示してください。『AIが担う業務』については、その実現方法も提案してください。」というプロンプトで、AIに素案を作成させています。
これは、現在全社で進められているAIタスクフォースの取り組みを、私たちが先行して実施したようなイメージです。そして、このビジョンに到達するために「半年ごとに何を実行していくか」を具体的に示したものが『AI-Native Roadmap』になります。
ーこのタイミングでロードマップが必要だと考えられた理由は何だったのでしょうか。
@Yuka:ハッカソンやProject Everyday AIを通じて進めてきたAI活用は、実現しやすいものから手を付けたので、部分的なものでした。私たちの業務全体を本格的にAI自動化していくにはどうすればよいか、体系的に考える必要があったため「ここからが本番だ」という意識で『AI-Native Roadmap』を作成しました。
成果を10倍・20倍にする横展開
@Yuka: 加えて、私たちが一貫して重視してきたのが全社への横展開です。LegalでのAIの活用事例や、AI推進のノウハウは、初めから他部署に共有する前提で、再現に必要な情報を揃えて作成していました。セミナー、ハッカソン、Project Everyday AI、AI-Native Roadmapの全ての情報について、資料を社内公開し、「わたしたちのノウハウをどうぞパクってください!」と社内へ展開しました。「Legalから全社に、起こせ、AIのBig Wave!」というスローガンのもと、Legal内に留まらず、広く横展開することで、成果を10倍、20倍にできるという意識を常に持っています。
@avaliu:その取り組みの一環として、ランチタイムに開催される社内勉強会で、私たちのe-ラーニング作成の事例などを紹介する機会がありました。発表後、実際に他部署の方から「ぜひこの方法を自分たちの部署でも使いたい」という連絡があり、部署間で連携が生まれたこともありました。会社全体のナレッジとして蓄積していく上で、横展開は非常に重要だと感じています。
AI時代の法務に求められるスキルと今後の課題
―さまざまな取り組みを経て、現在チームの働き方はどのように変わりましたか?
@seya: メルカリ社内の問い合わせに対応するAI Chatbot「Hiyochan」の導入は大きな変化の一つでした。導入当初は手探りでしたが、改善を重ねることで、社内手続きに関する問い合わせの一次対応がAIにかなり任せられるようになりました。これによって、私たちはより専門的な判断が求められる業務に集中できています。

@Yuka: 私が関連部署と協力して作成した「生成AI利用ガイドライン」はかなりの分量があるのですが、従業員がその全てに目を通し、私たちもガイドラインに応じて回答するといった運用に課題を抱えていました。そこで、この内容をすべてAIに読み込ませ、「質問があったらまずここに聞いてください」というAIによる質問回答ページ(NotebookLMを使用)を設置しました。これにより、従業員は長い文章を読み込む必要がなくなり、また、私たちも「ここでなんでも質問できます」と案内すれば済むようになり、大幅な省力化につながっています。
また、特許出願の領域でも活用しています。特許庁から届く拒絶通知に対して反論を検討する際、AIを活用することで、これまで人間が多大なコストをかけていた作業を大幅にスピードアップできました。
@avaliu: 私の業務では、個人レベルですがリサーチなどで頻繁にAIを使用しています。ハルシネーション(AIがもっともらしい嘘の情報を生成する現象)のリスクがあるため、最終的には人の目で条文などを確認しますが、AIが出力したリサーチ結果を参考にしながら結論を出す、という補助として利用しています。最近では、下請法の調査で、関連法規やガイドラインをすべてAIに読み込ませ、具体的な取引の条件が規制対象になるかを相談するといった使い方もしていますね。
また、チーム内では、Slack上のナレッジに特定のスタンプを押すだけで、要約されたうえで別シートへと蓄積される仕組みも構築しました。日々のやり取りが自動的に資産になる、とても便利な仕組みです。

@Yuka: AI時代に求められるスキルは確実に変わってきています。例えば、これまでの企業法務は文章をゼロから書く能力が重要でしたが、これからはAIといかに協業し、高いレベルのアウトプットを出すかが問われます。AIを「使いこなす」能力が不可欠になってくると思います。
―今後の課題についても教えていただけますか?
@Yuka:特に気になる課題は「若手の育成」です。これまで法務の若手は、単純作業も含めた反復経験を積むことでスキルアップしてきた側面がありましたが、今後はその部分をAIが代替するため、新しい育成方法を考える必要があります。
@avaliu: 「どの業務にどのAIを使うか」という見極めも重要です。AIにもそれぞれ得意・不得意があるので、その特性を理解し、試行錯誤していくことが求められますね。
AIは「難しい」ものではなく「楽しい!」もの
―最後に、これからAI活用に取り組む方々へメッセージをお願いします。
@Yuka: AIは、とにかく「楽しい」ツールです。そして、組織を変えるには、誰かがその楽しさに熱狂し、周りを巻き込んでいくことが不可欠。まずはあなたが「すごい!」と感動した体験を周りに広げ、ぜひその感動を共有してください。その”Wow!と思う体験”が、チームのマインドセットを変える強力なエンジンになるはずです。
@avaliu: 「AIに仕事を奪われるのではないか」と心配する方も多いと思います。しかし、AIの普及によって、新たな仕事や分野も必ず生まれる。恐れるのではなく、マインドセットを切り替え、新しい領域に自分の活躍の場を見出していくという感覚が、これからは非常に大切だと思います。

写真:タケシタ トモヒロ
この記事に関連する求人情報
募集中の求人の一部をご紹介します
-
Compliance Specialist – Mercoin
オフィス: 東京・六本木オフィス
会社・事業: メルコイン
-
AML Risk&Compliance Team Manager- Merpay / Mercoin
オフィス: 東京・六本木オフィス
会社・事業: メルペイ
-
Legal Specialist – Mercari/Crossborder
オフィス: 東京・六本木オフィス
会社・事業: メルカリ
-
知的財産スペシャリスト – Merpay/Mercoin
オフィス: 東京・六本木オフィス
会社・事業: メルペイ
-
プレエントリー / Pre Entry (NewGrads)
オフィス: 東京・六本木オフィス
会社・事業: メルカリ
別サイトに移動します
この記事に関連する求人情報
募集中の求人の一部をご紹介します
-
Compliance Specialist – Mercoin
オフィス: 東京・六本木オフィス
会社・事業: メルコイン
-
AML Risk&Compliance Team Manager- Merpay / Mercoin
オフィス: 東京・六本木オフィス
会社・事業: メルペイ
-
Legal Specialist – Mercari/Crossborder
オフィス: 東京・六本木オフィス
会社・事業: メルカリ
-
知的財産スペシャリスト – Merpay/Mercoin
オフィス: 東京・六本木オフィス
会社・事業: メルペイ
-
プレエントリー / Pre Entry (NewGrads)
オフィス: 東京・六本木オフィス
会社・事業: メルカリ
別サイトに移動します